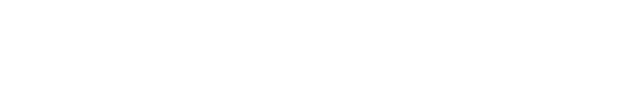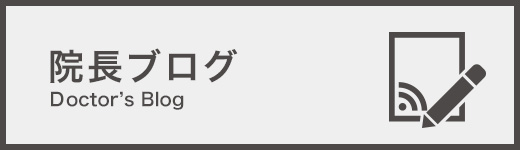生活習慣病 高血圧症
高血圧症治療について
1. 高血圧症とは
1.1 高血圧症の定義と基準
高血圧症状は一般に「高血圧」と呼ばれており、
血液が血管壁に加える圧力が高い状態を指します。
国内患者数は4300万人(日本人口の約3分の1)にのぼり、
本邦でもっとも多い疾患です。
高血圧症は、心臓と血管に負担をかけ、
長期間続くと心血管疾患や他の健康問題のリスクを高めます。
高血圧症の基準
- 収縮期血圧が140mmHg以上
- 拡張期血圧が90mmHg以上
のいずれかを満たす状態。
近年、ガイドラインでさらに基準が厳しくなりました。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 | ||
| 75歳未満 | 目標 | 130/80mmHg未満 |
125/75mmHg未満 |
| 75歳以上 | 目標 | 140/90mmHg未満 | 135/85mmHg未満 |
1.2 高血圧症の症状と特徴
ほとんどの場合、高血圧症には明確な症状がありません。
頭痛(特に早朝)やめまい、疲労感やふらつき(特に運動時)、頻尿や多尿(特に夜間)
などの症状が起こりえますが、必ずしも高血圧症と関連しているわけではありません。
症状が出るまで高血圧症を放置せず、早期発見と適切な治療を受け、高血圧症の合併症や健康リスクの軽減が重要です。
血圧とは
ところで血圧は下記2項目で規定されます。(心拍出量✕末梢血管抵抗)
- 心拍出量(血管内の血液の量)
- 抹消血管抵抗(血管の硬さ)
要するに
- 血液パンパン
- 血管カチカチ
だと血圧が高くなります。
すなわち、高血圧の治療とは
- 血液の量を減らし(血液パンパンを改善)
- 血管を柔らかくする(血管カチカチを改善)
ことにほかなりません。
2. 高血圧症の原因とリスクファクター
2.1 高血圧症の主な原因
2.1.1本態性高血圧症
ほとんど(8〜9割)の高血圧症はこちらです。
本態性高血圧症の原因はひとつではなく、
- 体型
- 食生活
- 運動習慣
- 睡眠習慣
- 遺伝的要素
などの総合的な結果として血圧が高くなります。
2.1.2二次性高血圧症
他の臓器の障害により引き起こされた高血圧症です。
- 腎機能障害
- 副腎など内分泌系統(ホルモンバランス)の異常
- 血管の病気
- 薬剤性
原因を解決してあげれば血圧の改善が期待でき、本態性高血圧症よりも若い方に多くみられます。
3. 高血圧症の診断と検査
3.1 高血圧症の診断基準と血圧の測定方法
血圧には
- 病院やクリニックで測定する診察室血圧
- 自宅で測る家庭血圧
- 専用機器で測定する24時間血圧
がありますが、本邦では専ら診察室血圧と家庭血圧が用いられます。
より重要性が高いのは家庭血圧です。
可能であれば、毎日、決まった時間(朝起床時など)に自宅で血圧計を用い測定してください。
血圧計は手首に巻くタイプよりも、上腕(二の腕)に巻くタイプの方が血圧の変動が少なくおすすめです。
| 家庭血圧目標値 | |
| 75歳未満 |
125/75mmHg未満 |
| 75歳以上 | 135/85mmHg未満 |
4. 高血圧症治療のアプローチ
4.1 高血圧症治療の目標と重要性
高血圧症の治療目標は、症状をとって楽になることではありません。高血圧症により引き起こされる将来的な臓器合併症、血管障害を予防することにあります。
症状がないから大丈夫、という考えは危険です。逆の言い方をすると、症状があってはいけないのです。
4.2 生活習慣改善と高血圧への影響
軽症の高血圧症であれば、初診時から薬を処方することは致しません。
食事療法、運動療法について説明し、再診まで経過を診ます。
薬が不要な状態で維持できればそれに越したことはありませんから。
4.3 食事療法と栄養管理
みなさんに最もとりくんで頂きたいのは食塩制限(減塩)です。血圧を下げたい方の場合、塩分接種目標は1日6g未満です。
減塩の例を下記に挙げます。
- 外食を避ける
- 過食を避ける
- 麺類のスープを飲まない(レンゲを使わない)
- 調味料はかけない(つけて食べる)
- 低塩・減塩の調味料を使う
- 香辛料や酢、果物を使う
- アルコールは飲まない・減らす
4.4 運動と高血圧管理
激しい運動よりは、軽く息が上がる程度の、速歩きやスロージョギング・ランニングのような有酸素運動が望まれます。
あまりきつい運動は逆に運動中の血圧を上げてしまいます。
4.5 薬物療法と治療薬の選択
生活習慣を改善しても目標値まで血圧が下がらない場合は、降圧薬を処方します。
降圧薬にはたくさんの種類がありますが、その作用は上記の通り
- 血管内容量を減らす(血液パンパンを改善)
- 血管の硬さやわらげる(血管カチカチを改善・予防)
ことで血圧を下げます。
みなさんの血圧値や全身状態、生活習慣などを考慮して最適な薬を選択いたします。
薬や通院を自己中断してしまうと、せっかくの治療効果がなくなってしまいます。できるだけ負担の少ない治療を提案いたしますので、ご相談下さい。
→主な降圧薬
5. 高血圧症と合併症
→高血圧症の合併症
参考記事
生活習慣病記事
管理栄養士記事